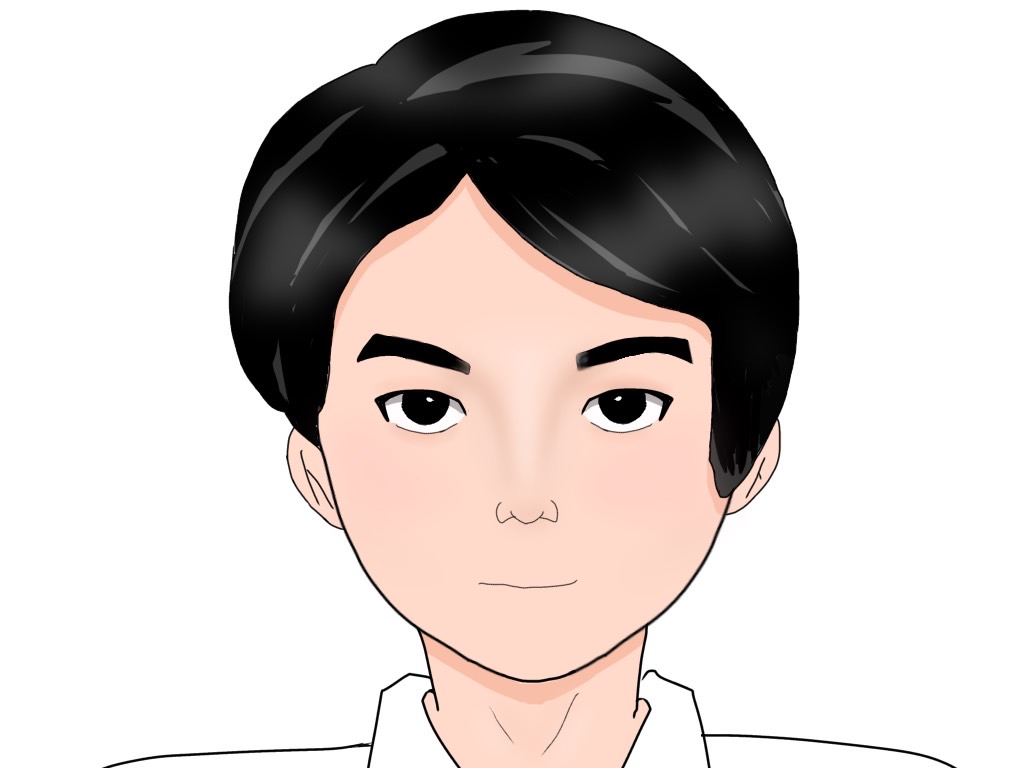9,600,000人
少数派の色覚特性を持つ者は、日本国内で、約320万人と推定されています。
これに本人の家族2名を加えると、約960万人、仮にそのうち8 割が18歳以上だとすると、768万票の大票田となります。
カリスマ性のある人物が顕れれば、相当の圧力団体になりうるかも知れません。
ただ、色覚特性少数派に関わる社会的な問題は、個々人の心の中の偏見と差別意識を、どのように取り除いていくかというものなので、強引なやりかたはそぐわないと思います。
力で、押さえつけた差別意識は、面従腹背を生むからです。
これに本人の家族2名を加えると、約960万人、仮にそのうち8 割が18歳以上だとすると、768万票の大票田となります。
カリスマ性のある人物が顕れれば、相当の圧力団体になりうるかも知れません。
ただ、色覚特性少数派に関わる社会的な問題は、個々人の心の中の偏見と差別意識を、どのように取り除いていくかというものなので、強引なやりかたはそぐわないと思います。
力で、押さえつけた差別意識は、面従腹背を生むからです。
1型2色覚当事者が作成したhQSLカード
 3色覚(正常色覚)の人にとって赤と緑は色相環で相対する補色の関係にあり、その違いは明白ですが、異常3色覚・2色覚のものにとっては、区別がつけにくい近似の色に見えます。
3色覚(正常色覚)の人にとって赤と緑は色相環で相対する補色の関係にあり、その違いは明白ですが、異常3色覚・2色覚のものにとっては、区別がつけにくい近似の色に見えます。赤と緑のほかにも、赤と茶色、緑と茶色、黄色と黄緑、青と紫、灰色とピンクなども苦手な配色になります。
また、淡いパステルカラーの配色も苦手です。
黒地に赤色文字、逆に赤地に黒色文字などの低コントラストもダメですし、白地に黄色の組み合わせのような、明度が似通った組み合わせもアウトです。
そんな私が作ったhQSLカードは、まずは高いコントラストと区別のつきやすい配色にすることを最優先にしています。
添付した、hQSLカードは、赤色や近似色を強調する目的には使わないように設定したつもりですが、参考にさせていただいた定義ファイルに含まれていたものが残っているかもしれません。
何かお気づきの点がありましたら、コメントでご指摘いただけたら幸いです。
あなたのエピソードをお寄せください。
色覚少数派の当事者自身、当事者の周辺の方のエピソードは、ネガティブなものもポジティブなものも、これから色覚特性(色覚多様性)と向き合う人々にとっては貴重な情報になります。
現時点では、色覚特性の医学的、科学的な情報は、WEB上に溢れていますが、当事者自身の体験談などについては比較的に少ないように思います。
少数派・多数派を問わず、あなたのエピソードをお寄せください。
ネガティブなもの、ポジティブなもの、どちらも歓迎します。
投稿にあたっては、このスレッドに対する返信ではなく、画面左上の「新規投稿」ボタンから新しいスレッドを立ててくださるようお願いいたします。
下記のリンクから掲示板に入れます。
色覚特性の情報交換掲示板
現時点では、色覚特性の医学的、科学的な情報は、WEB上に溢れていますが、当事者自身の体験談などについては比較的に少ないように思います。
少数派・多数派を問わず、あなたのエピソードをお寄せください。
ネガティブなもの、ポジティブなもの、どちらも歓迎します。
投稿にあたっては、このスレッドに対する返信ではなく、画面左上の「新規投稿」ボタンから新しいスレッドを立ててくださるようお願いいたします。
下記のリンクから掲示板に入れます。
色覚特性の情報交換掲示板