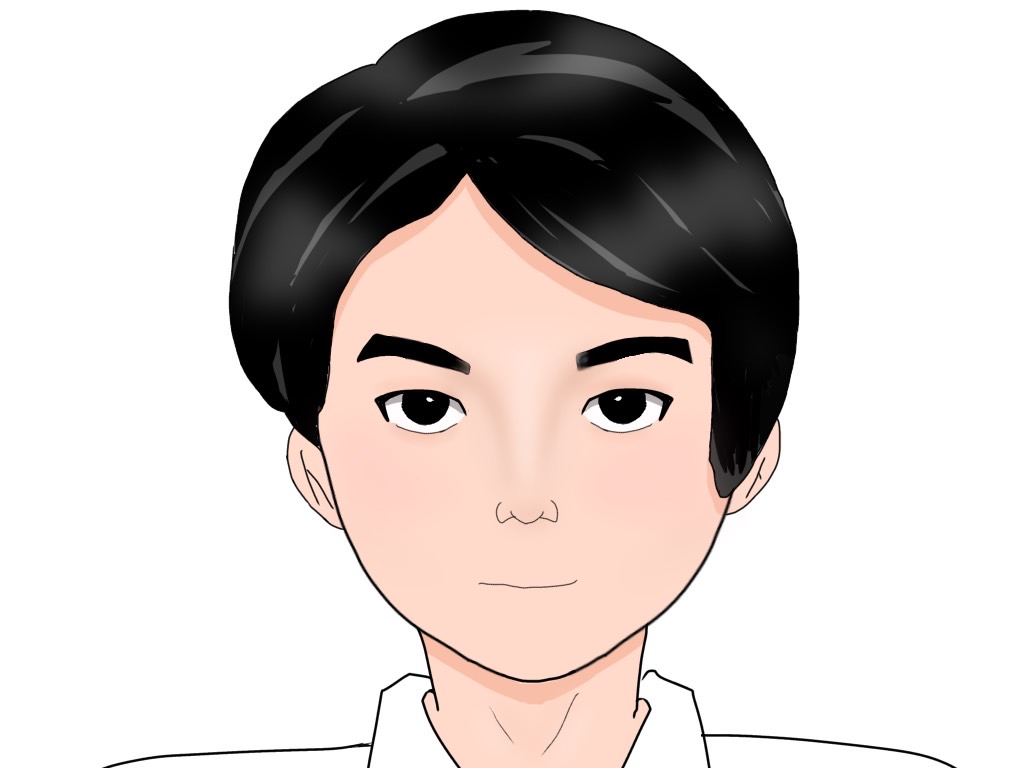紫色のLED道路案内標識 やるじゃないか国土交通省
やるじゃないか、国土交通省
今日久しぶりに圏央道の某インターチェンジ近くの国道を運転していて気がついたのだが、圏央道の混雑状況を案内するLED標識の表示が紫色になっていることを知りました。
以前は、これが赤色LEDだったため、1型2色覚者には表示そのものが読み取れなくて不安を感じていたので、とても嬉しく思いました。
紫色なら、多数派3色覚(正常色覚)でも、少数派の2色覚でも注意を喚起する色としてふさわしく感じます。
まだ、一部には赤色LEDを使った標示板が残っているので、1日も早く紫色のLEDに切り替えられることを切望します。
一度、赤色で設置したものを紫色に変えるわけですから、それなりのコストがかかります。申し訳なく思うと同時に、最初から色覚特性少数派の人間も参画させていれば避けることができたと思うと、ちょっと複雑な気持ちです。
今日久しぶりに圏央道の某インターチェンジ近くの国道を運転していて気がついたのだが、圏央道の混雑状況を案内するLED標識の表示が紫色になっていることを知りました。
以前は、これが赤色LEDだったため、1型2色覚者には表示そのものが読み取れなくて不安を感じていたので、とても嬉しく思いました。
紫色なら、多数派3色覚(正常色覚)でも、少数派の2色覚でも注意を喚起する色としてふさわしく感じます。
まだ、一部には赤色LEDを使った標示板が残っているので、1日も早く紫色のLEDに切り替えられることを切望します。
一度、赤色で設置したものを紫色に変えるわけですから、それなりのコストがかかります。申し訳なく思うと同時に、最初から色覚特性少数派の人間も参画させていれば避けることができたと思うと、ちょっと複雑な気持ちです。
お母さん自分を責めないで!
我が子の色覚特性が少数派(色盲色弱)であることを知ったときに
一番衝撃を受けるのは多くの場合母親です。
特に親類縁者に少数派の人がいないときはなおさらでしょう。
色覚特性について、色々と調べていくと自分に原因があることがわかり
子どもに申し訳ないと自分を責める人が多くいらっしゃいます。
しかし敢えて言います。
お母さん、決して自分を責めないでください。
お子さんは一時的にはあなたを怨むことがあるかもしれません。
でも、それはいつまでも続くわけではありません。
いずれは、自分自身の色覚特性を受け入れ母親への怨みは霧消します。
だれが悪いわけでもありません。
それよりも、多数派によってつくられた色に情報を載せるシステム自体を
変えていくことに注力することのほうが大切です。
一番衝撃を受けるのは多くの場合母親です。
特に親類縁者に少数派の人がいないときはなおさらでしょう。
色覚特性について、色々と調べていくと自分に原因があることがわかり
子どもに申し訳ないと自分を責める人が多くいらっしゃいます。
しかし敢えて言います。
お母さん、決して自分を責めないでください。
お子さんは一時的にはあなたを怨むことがあるかもしれません。
でも、それはいつまでも続くわけではありません。
いずれは、自分自身の色覚特性を受け入れ母親への怨みは霧消します。
だれが悪いわけでもありません。
それよりも、多数派によってつくられた色に情報を載せるシステム自体を
変えていくことに注力することのほうが大切です。
排除でなく共生の道を!
逆光で信号機の背後に太陽が位置しているとき、背面から太陽光を受けて、信号機に直接光が射し込んでいるとき....
ともに信号灯のどれが点灯しているのか判別できないことがあります。
特に逆光の場合は、多数派3色覚の人でもわからないことが多いと思います。
また、供用開始前の信号機にカバーが被されていないとき、あるいは故障で点灯していないときも不安になります。
赤色が暗く沈んだ色に見える1型2色覚者には、もしかしたら赤信号が点灯しているのかもと考えるからです。
そんなときは対向車線や歩行者用信号機の様子を見て判断しています。
これを聞いて、色覚特性少数派には、クルマの運転は任せられない、そんなふうにあなたはお考えになりますか?
何でもかんでも多数派に合わせてつくられた社会システムに合わない少数派は排除すれば良いとする社会は不健全な社会です。
少数派は排除して、代償にタクシー券を配布するといった短絡的な発想はご勘弁願いたいものです。
どうかこれからも色覚特性のことに限らず少数派との共生の道を考えてくださるようお願いします。
ともに信号灯のどれが点灯しているのか判別できないことがあります。
特に逆光の場合は、多数派3色覚の人でもわからないことが多いと思います。
また、供用開始前の信号機にカバーが被されていないとき、あるいは故障で点灯していないときも不安になります。
赤色が暗く沈んだ色に見える1型2色覚者には、もしかしたら赤信号が点灯しているのかもと考えるからです。
そんなときは対向車線や歩行者用信号機の様子を見て判断しています。
これを聞いて、色覚特性少数派には、クルマの運転は任せられない、そんなふうにあなたはお考えになりますか?
何でもかんでも多数派に合わせてつくられた社会システムに合わない少数派は排除すれば良いとする社会は不健全な社会です。
少数派は排除して、代償にタクシー券を配布するといった短絡的な発想はご勘弁願いたいものです。
どうかこれからも色覚特性のことに限らず少数派との共生の道を考えてくださるようお願いします。
言葉狩りは新たな差別的用語を生み出す
以前は、色盲・色弱あるいは色覚異常・色覚障害と云われていた、人たちをこの頃は「色覚特性」「色覚の多様性」と云うらしい。
でも、これっておかしくないですか?
本来、色覚特性や色覚多様性とは、所謂3色覚の人も含めて、「私の色覚特性は1型2色覚です」とか、「私の色覚特性は3色覚です」と使うのが筋というものではないでしょうか?
色覚の正常と異常との境界は、ここまでが正常、ここからが異常と劃然と分けられるものではないと云われます。
であるならば、色盲・色弱の人のみに「色覚特性」「色覚多様性」という言葉を使うのは、単なる言葉狩りに堕してしまいます。
色盲・色弱の色覚特性を持っている人がそれを望んでいるとは思えません。
それでは、色覚特性・色覚多様性という言葉は、新たな差別的用語になるだけです。
でも、これっておかしくないですか?
本来、色覚特性や色覚多様性とは、所謂3色覚の人も含めて、「私の色覚特性は1型2色覚です」とか、「私の色覚特性は3色覚です」と使うのが筋というものではないでしょうか?
色覚の正常と異常との境界は、ここまでが正常、ここからが異常と劃然と分けられるものではないと云われます。
であるならば、色盲・色弱の人のみに「色覚特性」「色覚多様性」という言葉を使うのは、単なる言葉狩りに堕してしまいます。
色盲・色弱の色覚特性を持っている人がそれを望んでいるとは思えません。
それでは、色覚特性・色覚多様性という言葉は、新たな差別的用語になるだけです。
一灯点滅式信号機
1型2色覚者にとって、一灯点滅式の交通信号機は苦手な存在だったが、多数派3色覚にとっても鬼門だった?
1型2色覚者が、一灯点滅式の交通信号機を苦手で危険な存在としているのは、何よりも黄色と赤色の弁別ができないという点にある。
自分が徐行して進むべきなのか、それとも一時停止をするべきなのかがわからない。
後続車のドライバーが多数派3色覚だと仮定すれば、可能なら先に行ってもらうが、そうでなければたとえ黄色の点滅でも、最徐行で進行して後続車を牽制しつつ一時停止をするが、常に追突されるリスクを侵さなければならない。
この、一灯点滅式信号機は、1984年に福岡市南区に誕生し、2015年には5,904基に達したが、同年12月に警視庁が、一時停止標識で代替できる場合は撤去を検討するよう指示したことから、漸減しているとのことだ。
その理由は、老朽化による維持コストの増大、赤色に点灯する一時停止標識やカラー舗装の普及などのほか、一灯点滅式信号機に馴染みのないドライバーが曖昧に判断してしまうなどで事故を誘発してしまうことなどが上げられるという。
実際、一灯点滅式信号機を撤去したことにより事故率が低下しているそうだ。
特に色覚特性少数派のために、一灯点滅式信号機の撤去を進めていることではないようだが、結果として、色覚特性少数派の安全に寄与しているなら歓迎すべきことだ。
(出典)
https://www.webcartop.jp/2022/12/1019541/
1型2色覚者が、一灯点滅式の交通信号機を苦手で危険な存在としているのは、何よりも黄色と赤色の弁別ができないという点にある。
自分が徐行して進むべきなのか、それとも一時停止をするべきなのかがわからない。
後続車のドライバーが多数派3色覚だと仮定すれば、可能なら先に行ってもらうが、そうでなければたとえ黄色の点滅でも、最徐行で進行して後続車を牽制しつつ一時停止をするが、常に追突されるリスクを侵さなければならない。
この、一灯点滅式信号機は、1984年に福岡市南区に誕生し、2015年には5,904基に達したが、同年12月に警視庁が、一時停止標識で代替できる場合は撤去を検討するよう指示したことから、漸減しているとのことだ。
その理由は、老朽化による維持コストの増大、赤色に点灯する一時停止標識やカラー舗装の普及などのほか、一灯点滅式信号機に馴染みのないドライバーが曖昧に判断してしまうなどで事故を誘発してしまうことなどが上げられるという。
実際、一灯点滅式信号機を撤去したことにより事故率が低下しているそうだ。
特に色覚特性少数派のために、一灯点滅式信号機の撤去を進めていることではないようだが、結果として、色覚特性少数派の安全に寄与しているなら歓迎すべきことだ。
(出典)
https://www.webcartop.jp/2022/12/1019541/